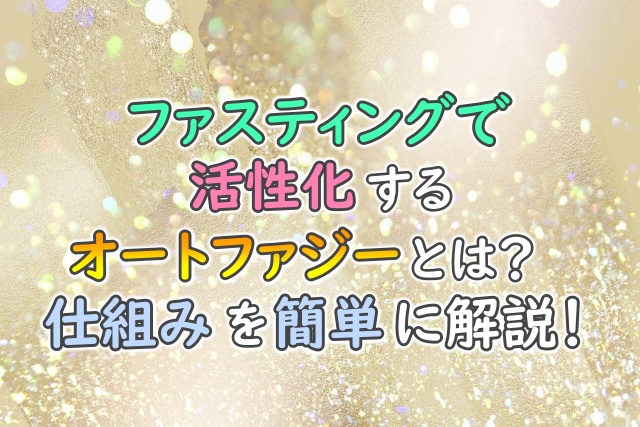
ファスティング(断食)で活性化するオートファジーって何?
大隅良典氏がノーベル賞を受賞したみたいだけど、どんな働きがあるか知りたい
人のカラダにどんな効果があるのかも教えて!
こんな疑問にお答えします。
本記事の内容
- ファスティング(断食)で活性化するオートファジーについて徹底解説
- ファスティング(断食)で活性化するオートファジーの効果3選
- ファスティング(断食)とあわせて行うオートファジーを活性化させる3つの習慣
本記事の執筆者
ファスティングアドバイザーのシュンです。
私はファスティングの資格をもっています。
2018年に体調不良がきっかけでファスティング(断食)を生活習慣に取り入れました。
意識的に空腹の時間をつくり空腹力を鍛えれば、自然治癒力が高まり元気で健康なカラダが手に入ります。
プロフィール
「オートファジーって聞いたことあるけど、どんな働きをするのかよくわからない」という方が多いのではないでしょうか?
本記事では、ファスティング(断食)で活性化するオートファジーについて、具体的にわかりやすく解説していきます。
あなたがファスティング(断食)を行いオートファジーを活性化すれば下記のようなメリットがあるでしょう。
- 生活習慣病を予防し医療費を節約できる
- 5年後、10年後も健康なカラダで生きられる
- 老化を遅らせ実年齢よりも見た目が若くなる
ぜひ、あなたもファスティング(断食)でオートファジーを活性化し病気や不調、老化を遠ざけ、元気で健康なカラダを維持してください。
なお、ファスティング(断食)や1日1食、16時間断食を行うなら酵素ドリンクがオススメです。
酵素ドリンクを使うと寺で行う苦行のような断食ではなく、自宅で無理なく安全にファスティングができます。
また、ファスティング(断食)中の食べ物が食べれないとうストレスを軽減できます。
酵素ドリンクについては、下記の記事を参考にしてみてください。
クリックできる目次
ファスティング(断食)で活性化するオートファジーについて徹底解説
ファスティング(断食)で活性化するオートファジーついて、下記の順序で解説していきす。
- オートファジーの仕組みを簡単に解説
- オートファジーに関する論文数が激増
- オートファジーの3つの役割
1つずつ具体的に解説していきますね。
オートファジーの仕組みを簡単に解説
オートファジーとはギリシャ語でauto「自分自身」、phagy「食べること」という言葉を組み合わせて「自分自身を食べる」という意味があります。
日本語では「自食作用」と言われています。
オートファジーは1960年代にベルギーの生化学者クリスチャン・ド・デューブ氏によって発見されました。
しかし、当時オートファジーの詳細なメカニズム(仕組み)については解明されなかったのです。
時は流れてオートファジーのメカニズム(仕組み)を分子レベルで解明したのが、東京工業大学・大隅良典(おおすみよしのり)栄誉教授です。
その功績が認められ2016年3月10日にノーベル医学・生理学賞を受賞されました。
オートファジーとは端的に説明すると細胞内のゴミを分解して再利用(リサイクル)する一連のプロセスのことです。
人間の体は一説によると約37兆個の細胞で構成されています。
細胞の中は細胞内小器官(オルガネラ)とタンパク質でぎっしりつまっています。
その細胞内の1つ1つでオートファジーのメカニズム(仕組み)が働いています。
オートファジーのメカニズム(仕組み)が働く条件は空腹時です。
人間が空腹状態になると細胞内で隔離膜という二重の膜が出現します。
この隔離膜が細胞内のゴミ(異常タンパク質や不良ミトコンドリア、病原菌)などを包み込み球状になります。
この球状をオートファゴソームといいます。オートファゴソームとは言い換えれば細胞のゴミ収集車のようなものです。
次に多種類の分解酵素を含んだ分解工場といわれるリソソームとオートファゴソームが、融合しオートリソソームとなります。
そして、オートリソソームで異常タンパク質や不良ミトコンドリア、病原菌が分解されアミノ酸となります。
分解されたアミノ酸はタンパク質の材料やエネルギー源として、また体内で再利用(リサイクル)されます。
こうした細胞内で起こる一連のメカニズム(仕組み)をオートファジーと言います。
ちなみに人が1日に体内でタンパク質を合成する量は200gです。
しかし、1日に食事で摂るタンパク質は70gです。
この不足している130gのたんぱく質はオートファジーの働きで細胞内のゴミを再利用して補っています。
つまり、人間の1日に必要とするタンパク質は、ほとんどがオートファジーのリサイクル(再利用)によって作らているのです。
オートファジーに関する論文数が激増
ここ10年の間にオートファジーに関する論文の数が激増しています。
1990年代には世界で発表されるオートファジーに関する論文の数は年間、数十本程度でした。
しかし、2010年になると論文数は年間2000本、2020年には年間8000本ものオートファジー関連の論文が発表されています。
また、世界のどこかで毎月、オートファジーに関する国際会議が開かれているそうです。
このような状況は近年、研究者を始め一般の人たちにもオートファジーの関心が高まっていることを示しています。
オートファジー3つの役割
オートファジーには体内で3つの役割があります。
- 飢餓に耐えるための栄養素作る
- 細胞内の大掃除
- 病原体の除去
1.飢餓に耐えるために栄養素を作る
人間は飢餓状態になるとオートファジーが作用して、体内から栄養素を作り出します。
まず、空腹状態になると肝臓や筋肉に貯蔵されたグリコーゲンを、グルコース(糖)に変換してエネルギーとして利用します。
次に肝臓や筋肉のグリコーゲンが枯渇すると、体脂肪を分解し肝臓でケトン体に変換してエネルギーとして使われます。
ケトン体について知りたい方はファスティング(断食)で増えるケトン体とは?いつから増えるの?にて詳しく解説しています。
エネルギー源といえばブドウ糖ですが、代替エネルギーのケトン体はブドウ糖以上に優れものです。
このように飢餓状態になっても体内で栄養素を作り出せるので、水分を摂ればある程度は生きられるのです。
マウスの実験でオートファジーが機能しない、新生児のマウスの赤ちゃんを遺伝子操作で作りました。
お腹の中にいるときは母親の胎盤から栄養補給をしてましたが、切り離した12時間後に亡くなってしまったのです。
一方、オートファジーが正常に機能するマウスの赤ちゃんは、肝臓や筋肉でアミノ酸を自ら作り出し12時間後も栄養不足になることもなく生存しました。
こうしたマウスの実験からもわかるように、オートファジーは生命維持に欠かせないシステムなのです。
2.細胞内の大掃除
オートファジーは細胞内をキレイに大掃除して、細胞内の品質管理を保つ働きもあります。
細胞内に存在するミトコンドリアやタンパク質は、時間がたつと劣化し悪くなってきます。
劣化した不良ミトコンドリアは、病気や老化の原因になる活性酸素を発生させます。
こうした細胞内のゴミをキレイにお掃除してくれるのが、オートファジーのメカニズム(仕組み)です。
具体例をあげると、マウスの実験で脳だけオートファジーが働かないマウスを作りました。
すると2週間後に脳にゴミがたまり、そのマウスは動けなくなってしまったのです。
このように細胞内でオートファジーが機能することで、毎日、健康に生きられるのです。
なお、エネルギー発電所のミトコンドリアについては、ミトコンドリアを増やすにはファスティング(断食)がいい3つの理由とは?を参考にしてみてください。
3.病原体の除去
オートファジーの3つ目の役割はウイルスや細菌などの病原体を除去する働きがあります。
血液に侵入してきた病原体は免疫細胞によって除去されます。
そして、細胞内に侵入してきた病原体はピンポイントで、オートファジーが除去してくれるのです。
全細胞に免疫機能が備わっていることが判明したことで、感染症学・免疫学において歴史的な大きな一歩と言われています。
このようにオートファジーの機能は、病原体から細胞を守ってくれるので心強いですね。
ファスティング(断食)で活性化するオートファジー効果3選
ファスティング(断食)などで体の細胞のオートファジーを活性化させると、以下の嬉しい3つの効果が得られます。
- ①:病気の予防と健康の維持・増進
- ②:老化の予防と美容・美肌効果
- ③:ダイエット効果
では、1つずつ解説していきます。
1.病気の予防と健康の維持・増進
オートファジーが活性化すると、体の細胞修復、毒素の除去、免疫力の強化などの効果があります。
つまり、体の細胞が悪い方に進行するのを抑えられるので、病気の予防、健康の維持・増進につながるのです。
一方で、暴飲暴食するとmTORE(エムトア)のスイッチが入ります。
mTORE(エムトア)とは細胞が成長モードに入り、タンパク質や脂肪などの細胞が増幅することです。
mTORE(エムトア)のスイッチが入るとオートファジーのスイッチがオフになります。
すると、細胞の自己浄化や細胞修復の機能が働かなくなります。
その結果、細胞の慢性炎症と毒素の蓄積で、免疫力の低下と生活習慣のリスクを高めます。
このようにオートファジーの活性化は病気の予防、健康の維持・増進に効果的です。
一方で、オートファジーのスイッチが継続的にオフになると、老化の促進や病気のリスクが高まるのです。
2.老化の予防と美肌効果
オートファジーの2つ目の効果は老化の予防と美肌効果です。
なぜ、オートファジーが活性化すると老化の予防と美肌に効果があるのでしょうか?
それは体内で発生する活性化酸素を除去するからです。
活性酸素は大量に発生すると、シミやシワなどが増え細胞の老化を促進させる原因になります。
例えば、細胞内小器官(オルガネラ)のミトコンドリアは、劣化すると大量に活性酸素を発生させます。
オートファジーは劣化した細胞内小器官(オルガネラ)を、回収し分解し再利用(リサイクル)してくれます。
そのため、活性酸素の発生を抑えられるので、肌の老化を予防し美肌効果につながるのです。
また、オートファジーが活性化する条件は食事制限ですが、長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)が活性化する条件でもあります。
マウスの実験で食事を6割に制限したところ、長寿遺伝子が活性化し寿命が1.3倍も延びたと報告されています。
人間の寿命が80歳とすると、24年も寿命が延長することになりますね。
長寿遺伝子はカロリー制限をすると細胞小器官(オルガネラ)のミトコンドリアからNDAという補酵素が大量に放出されます。
その放出されたNDA補酵素が細胞核の長寿遺伝子にまとわりつき、長寿遺伝子にスイッチが入ります。
ドラゴンボールで例えるなら、悟飯がセルとの闘いでスーパーサイヤ人に覚醒するような感じです。
ちなみに補酵素のNDAとはニコチンアミドアデニンジヌクレオチドの略です。
このようにオートファジーを活性化することで、長寿遺伝子のスイッチが入り、老化の予防と美肌効果が期待できるのです。
長寿遺伝子については、ファスティング(断食)で若返り遺伝子が活性化?サーチュインの効果とは?にて詳しく解説しています。
3.ダイエット効果
オートファジーを活性化するとダイエット効果も期待できます。
なぜなら、オートファジーを活性化するには、空腹の時間を作る必要があるからです。
空腹の時間を作ると内臓脂肪が燃焼し、ダイエット効果が得られます。
また、精製された糖質は控えめにする必要があります。
その理由は精製された糖質は、血糖値スパイクを起こし、血糖値をさげるためにインスリンが過剰に分泌されるからです。
インスリンの過剰分泌は、オートファジーの働きを抑制し下記のようなデメリットがあります。
- 脂肪細胞が増える
- 血管を傷つけ動脈硬化を促進させる
- 老化を加速させる
- 癌細胞が増える
オートファジーを活性化するには、精製された糖質は控えめにしましょう。
ちなみに血糖値スパイクを起こさない食べ物は下記のとおりです。
- 玄米
- サラダや果物
- 海藻類、キノコ類
- 発酵食品(味噌・漬物)
- はちみつ
食物繊維が豊富なヘルシーな食事をすることでオートファジーが活性化します。
なぜかというと、血糖値が急激に上がる食品ではないので、インスリンの大量分泌がないからです。
したがって、オートファジーの活性化を意識した食生活にすると、自然と脂肪が燃焼しダイエット効果につながります。
下記の記事もあわせてご覧ください。
ファスティング(断食)とあわせて行うオートファジーを活性化させる3つの習慣
ファスティング(断食)とあわせて行うオートファジーを活性化させる3つの習慣は以下になります。
- 1日1食や16時間断食を行う
- 腹7分で「ま・ご・わ・や・さ・し・い」を中心の食生活
- 軽い有酸素運動をする
①:1日1食や16時間断食を行う
1日1食や16時間断食を定期的に実践すれば、オートファジーを活性化できます。
2~3日間のファスティング(断食)を行うよりハードルが低いため実践しやすかと思います。
16時間断食でもハードルが高い人は、12時間断食から始めてみるのがいいでしょう。
以前は1日3食、食べることが一般常識でした。
しかし、近年、研究が進み1日3食は食べすぎなのではないかという意見もあります。
常に消化器官が消化活動に追われて、内臓疲労が蓄積されます。
特に衰えを実感する30代後半~40代にかけては食生活を見直すことが大切です。
実際、日本では糖尿病患者は予備軍を含めると2000万人を超えています。
また、ガン、認知症も増える一方で、生活習慣で悩まされている人は増加の一途をたどっています。
さらに、酵母菌やマウス、アカゲザルなど人間と同じ真核生物の実験でも、カロリー制限することが、病気や老化の予防になり健康長寿の傾向があると研究結果がでています。
したがって、生活習慣病を予防するためにも1日2食の16時間断食の実践が効果的と考えられています。
実際、僕も体調崩してからは、1日1.5食か1日2食を心がけるようになり体調を崩すことがなくなりました。
40代のカラダには1日1.5食だと調子がいいです😄
ドイツの古い諺に「1日3食のうち2食は自分のため1食は医者のため」という言葉があります。
つまり、ドイツの諺は食べすぎは病気になることを示唆していますね。
16時間断食のやり方については、16時間断食の正しいやり方【ダイエットを成功させる2つの秘訣】を参考にしてみてください。
②:腹7分で「ま・ご・わ・や・さ・し・い・こ」中心の食生活
腹7分で「ま・ご・わ・や・さ・し・い・こ」中心の食生活もオートファジーの活性化におすすめの習慣です。
日本の諺には「腹八分目で医者いらず」という言葉があります。
ヨガの格言に「腹八分で医者いらず、腹六分で老いを忘れる、腹4分で仏に近づく」という格言もあります。
また、マサチューセッツ工科大学のレオナルド・ガレンテ教授の長寿遺伝子の研究では次のような研究結果が報告されています
腹6分~7分にカロリー制限をしたマウスに長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)の活性化が見られたという研究結果です。
つまり、食事を腹6分~8分程度に抑えることが、病気や老化の予防につながることを示しています。
それと、まごわやさしいこの食材を中心に食べることです。
なぜなら、天然の糖質、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ファイトケミカル、食物酵素、食物繊維などが豊富だからです。
また、植物性の食品は内臓にやさしく消化にもいいからです。
まごわやさしいこについてはファスティング(断食)後の回復食で失敗しない食べ方【食材・メニューも紹介】にて詳しく解説しています。
③:軽い有酸素運動をする
軽い有酸素運動をするとオートファジーが活性化する方法の1つです。
アメリカの研究グループのマウスの実験で証明されています。
運動させたマウスと運動させないマウスを比較しました。
すると、運動させたマウスの筋肉や心臓、肝臓などの臓器でオートファジーが活性化しているのが確認されたのです。
一方で、過度の運動は逆に体内で活性酸素が発生し、細胞にダメージを与えるリスクがあるので注意が必要です。
まとめ:ファスティング(断食)のオートファジーで健康維持につながる
今回は『ファスティング(断食)で活性化するオートファジーの仕組み』について解説しました。
最後におさらいのために本記事の概要をまとめます。
ファスティング(断食)で活性化するオートファジーの仕組み
- 飢餓状態になるとオートファジーが活性化する
- ゴミ清掃車のオートファゴソームが細胞内のゴミを回収する
- 回収したゴミを分解し、リサイクル工場のリソソームに運搬する
- リサイクルされた細胞のゴミはタンパク質やエネルギー源として再利用される
オートファジーの役割
- 飢餓に耐えるために栄養素を作る
- 細胞内の大掃除
- 病原体の除去
オートファジーの効果
- 病気の予防と健康の維持・増進
- 老化の予防と美容・美肌効果
- ダイエット効果
オートファジーを活性化する3つの習慣
- 定期的に1日1食や16時間断食を行う
- 腹7分で「ま・ご・わ・や・さ・し・い」中心の食生活
- 定期的な軽い有酸素運動をする(ランニング、ウォーキングなど)
オートファジーの活性化は肥満、生活習慣病などの予防に効果があるとマウスの実験で実証されています。
僕も日ごろオートファジーの活性化を意識して生活しているため、40代に入りましたが元気に過ごせています。
ファスティング(断食)というと栄養失調と辛い空腹感が不安ですよね。
そんな不安を解消してくれるのがファスティング(断食)専用の酵素ドリンクです。
酵素ドリンクについては下記の記事をご覧ください。
